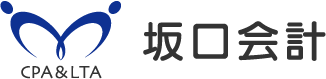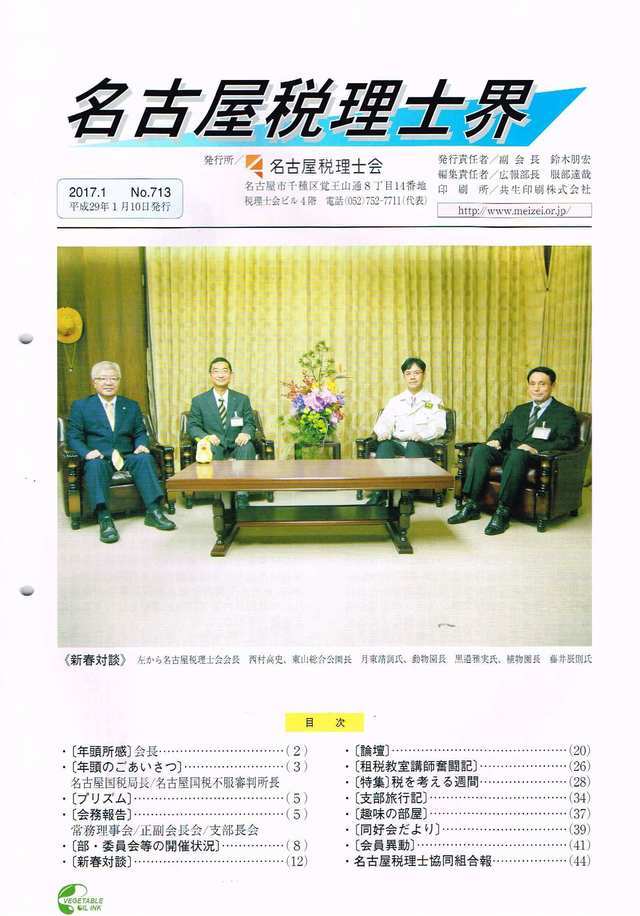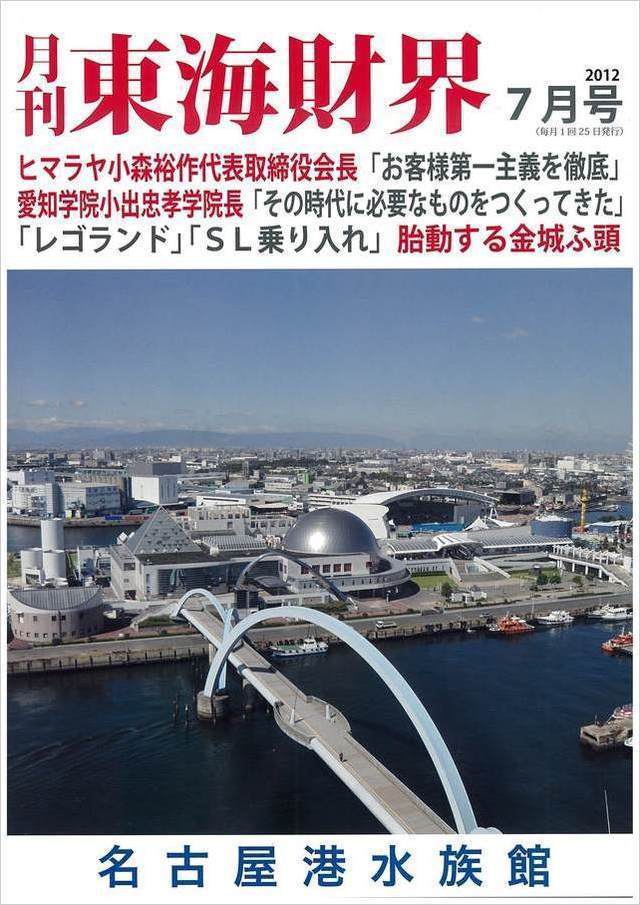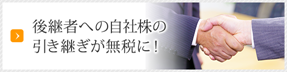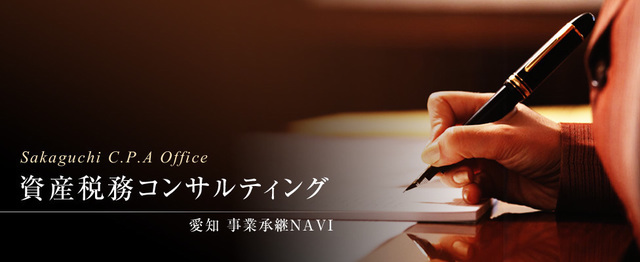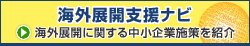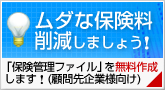愛知県大府市の公認会計士・税理士 坂口美穂事務所。皆さまの最適なファイナンス構築と企業価値向上を支援する会計事務所です。
資産の流動化の仕組み
流動化の概要
資産の流動化」とは
資産の流動化とは、債権や不動産などの資産を保有する者(オリジネーター)が、特定の資産を保有することを目的として便宜上の器(これをヴィークルという)を使った仕組みを作り、その資産をヴィークルに譲渡してオフバランス化し、その資産が生み出す将来のキャッシュ・フローを原資として資金調達を行う方法であり、対象資産によって、債権流動化または不動産流動化などと呼ばれます。
また、資産の流動化のうち、対象資産を有価証券化し、資金調達を行う方法を資産の証券化といいます。
資産の流動化・証券化のメリット
資産の流動化・証券化は、元来流通性・流動性が低かった資産に流動性を付与するとともに、資金調達を望む資産保有者や投資者等に以下のようなメリットをもたらします。
① 資金調達の多様化
不動産証券化は、オリジネーターの信用力に依存しないため、格付けの低い会社でも、証券化する資産が優良であれば、その資産の信用力に依拠した有利な条件による資金調達が可能となります。このような資産の信用力に依拠した資金調達は、企業の信用力に依拠した資金調達(コーポレート・ファイナンス)に対してアセット・ファイナンスと呼ばれることがあります。
② リスクの移転
資産を証券化することにより、当該資産を保有し続けることにより生じるさまざまなリスクを投資者等の第三者に移転することができます。一方で投資家等にとっては投資選択の幅が広がり投資機会が増大することになります。
③ 財務指標の改善
証券化した資産のオフバランス化により貸借対照表がスリム化されるとともに基本的に連結対象からも外れることから、総資本利益率や自己資本比率といった経営指標(財務指標)を向上させることが可能となります。特に、含み益のある資産を証券化することにより潜在的な企業収益力損益計算書上に顕在化させることが可能となります。
SPE(特別目的事業体)の概要
SPEとは
SPE(特別目的事業体:Special Purpose Entity)とは、資産の流動化に使用されるヴィークルの1つであり、流動化の対象とされる特定資産をオリジネーターから分離し、当該資産に係る将来キャッシュ・フローに依拠した資金調達のために、原資産と投資家をつなぐ導管体としての役割を担う仕組みとして組成される事業体のことをいいます。この目的を達成するためにSPEのなしうる業務内容は、定款上の記載のみでなく、契約上、組織上であらかじめ定められた権限の範囲内に限定されることになります。
また、SPEは、法律上は譲渡人から独立しているものの、経済的には流動化の対象資産から生じるキャッシュ・フローを変換する等の特定の目的のためだけに存在する実体のない導管体にすぎません。なお、SPEと同義での用語としてSPV(Special Purpose Vehicle)と呼ぶ場合もあります。
SPEとして会社が活用された場合にはSPCと呼ばれ、さらに「資産の流動化に関する法律」(資産流動化法)に従って設立された場合には「特定目的会社」(一般にTMKと呼ばれることもある)といい、資産流動化法に従って設定された信託の場合には「特定目的信託」(一般にTMSと呼ばれることもある)と呼ばれます。いずれにしても、SPEの定義の中に包含される事業体であり、本質的に変わることはありません。
資産流動化型ヴィークルと資産運用型ヴィークル
集団投資スキームとしての不動産証券化は、以下の2つのヴィークルに区分されます。この区分により、適用される法律・会計上の取扱い、利用されるヴィークルも異なるうえ、対象とする不動産の入替えが可能か否かにも影響するため、証券化の目的を十分吟味してスキームを選択する必要があります。
① 資産流動化型ヴィークル
所有者(オリジネーター)が、不動産を証券化という手法を使ってSPEにその不動産を譲渡してオフバランス化し、その不動産の将来の収益性を原資に資金調達を行うものであり、「モノありき」の証券化ともいわれます。このタイプの法定スキームとしては、特定目的会社(会社型)および特定目的信託(契約型)があり、これらは原則としてあらかじめ資産流動化計画に定められた行使しかできず、資産の売買について裁量がほとんどありません。証券化の代表例としては、企業が本社ビルなどを証券化する場合などが該当します。
② 資産運用型ヴィークル
最初に投資家の資金を集めてファンド化し、これを元手に不動産を投資して運用益を投資家に分配していくものであり、①に対して「カネありき」の証券化ともいわれます。このタイプの法定スキームとしては投資法人(会社型)および投資信託(契約型)があり、資産の入替えによる継続的運用を予定しています。J-REITやプライベートファンドが、このタイプのSPEとして活用される代表例です。実際には、法定スキーム以外にも合同会社、特例有限会社、株式会社、外国会社の国内支店、LLC等のヴィークルを利用したスキームもあります。
法定4ヴィークルの導管性確保の基本的要件
資産流動化法に基づき設立される特定目的会社、J-REITに用いられる投資法人等のいわゆる法定4ヴィークル(特定目的会社、特定目的信託、投資法人および特定投資信託のことをいう)は、配当損金算入要件を満たすことにより、その投資家に対して支払われる配当の額を税務上の損金の額に算入することができるという特典を与えられたヴィークルです。法定4ヴィークルはこの特典により、課税所得を非常に少額にすることができるため、結果として法人税等の税負担を非常に少なくすることが可能となります。
なお、ここでは、法定4ヴィークルのうち、特定目的会社における損金算入要件を記載します。
資産流動化計画を遵守しているこ資産流動化計画を遵守しているこ(Ⅰ)対象法人の要件 (全ての要件を満たすこと) | ① 特定目的会社の名簿に記載されているものであること ② 次のいずれかに該当するものであること イ)その発行をした特定社債の発行価額の総額が1億円以上であるもの ロ)その発行した特定社債が機関投資家または特定債権流動化特定目的会社により保有されることが見込まれていること ハ)その発行をした優先出資が50人以上の者によって引き受けられたもの ニ)その発行をした優先出資が機関投資家のみによって引き受けられたもの ③ 優先出資および基準特定出資の50%超が国内募集である旨が資産流動化計画に記載されていること ④ 会計期間が1年を超えないものであること |
(Ⅱ)対象事業年度の要件 (全ての要件を満たすこと) | ① 資産流動化計画を遵守していること ② 他の業務を営んでいる事実がないこと ③ 特定資産を信託財産として信託していることまたは特定資産の管理および処分業務を他の者に委託していること ④ 事業年度終了の時において、一定の同族会社に該当していないこと(上記(Ⅰ)②イまたはロに該当するものを除く。)⑤ 他の業務を営んでいる事実がないこと ⑥ 特定資産を信託財産として信託していることまたは特定資産の管理および処分業務を他の者に委託していること ⑦ 事業年度終了の時において、一定の同族会社に該当していないこと(上記(Ⅰ)②イまたはロに該当するものを除く。) |
(※)【配当可能利益】
配当可能利益=税引前当期純利益-前期繰越損失-減損損失×90%
【特定社債の発行がある場合】
上記の金額からさらに下記ⅰ)、ⅱ)の金額を控除した金額
ⅰ)(当期に償還した特定社債の額-当期損金算入減価償却費)×2
ただし、特定資産譲渡等を行った場合は((当期に償還した特定社債の額-特定資産譲渡等調達資金充当額)-当期損金算入減価償却費)×2とする。
ⅱ)期末特定社債の残高×5%-期首繰越利益積立金額
特定目的会社の特徴
特定目的会社は、一般的に以下のような特徴を満たすスキームにて組成されています。
非連結
特別目的会社(特定目的会社および事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう)については、支配力基準の例外として一定の要件を満たすものについては、当該特別目的会社の出資者および譲渡人から独立しており、それらの子会社には該当しないものと推定する規定が設けられています(財務諸表等規則8条7項)。
導管性(二重課税の排除)
投資家にとっては、実物不動産に直接投資をすれば投資収益に対して直接課税されるのみですが、別会社を経由して投資する場合、不動産から生まれる収益はいったんその会社の収益としてプールされ、それを配当として分配するため、特定目的会社の段階での利益への課税と投資家段階での配当への課税の二重課税が生じてしまうという問題があります。
証券化商品としては、このような二重課税を排除する必要がありますが、特定目的会社については、一定の要件を満たせば利益の配当の額を損金に算入することができるため、課税される利益は少額になり、均等割など多少の税金は発生するものの、ほとんど税金を課せられることなく、投資不動産から得られた収益のほとんどを投資家に配当することができます。
このほかにも、特定目的会社については、一定に要件を満たせば不動産取得税や登録免許税など流通税についても軽減の措置があり、特定目的会社の段階での課税を軽減する仕組みが法律上も整備されているが、これらの二重課税の排除のためには厳格な要件があるため、十分に注意する必要があります。
倒産隔離
① オリジネーターからの倒産隔離
特定目的会社については、投資家はあくまで特定資産の収益性に対して投資をしているため、オリジネーターの信用リスクを遮断しなければなりません。
つまり、オリジネーターが倒産した場合にも、オリジネーターの債権者が特定目的会社の特定資産を差し押さえるなどできないように組成する必要があります。そのためには、法的な対抗要件の具備や、人的遮断(第三者を取締役にする)などの処置がなされているのが一般的です。
② 債権者・株主または役員からの倒産隔離
特定目的会社についても、債権者、株主または役員が破産等の申立てを行うことにより倒産することは十分に考えられます。そのための対策として、業務が流動化計画に基づくものに制限されていることや、役員等が倒産の申立てを行わないことについての誓約書を債権者に提出するなどの対策が一般的です。
信用補完
特定目的会社については、投資対象を絞るなど、基本的のリスクを限定した仕組みがとられているが、それでも投資家等が資金提供を行いやすいようにするため、信用補完の仕組みが組み込まれている場合が多いです。代表的な信用補完の仕組みとしては、以下のものが挙げられます。
① 優先劣後構造
特定社債や特定目的借入れの中に優先・劣後の区分を設け、劣後部分をオリジネーターなどアレンジを行う側のプレーヤーが保有し、優先部分を投資家に販売します。つまり、劣後部分の存在が信用補完となります。
② セラーリザーブ
オリジネーターがヴィークルに資産を譲渡する際に、一定割合をオリジネーターに留保して、キャッシュ・フローが不足した場合にはオリジネーターが負担する仕組みをとることです。なお、会計上譲渡が認められる要件として、オリジネーターのリスク負担割合が5%以下である必要があるため、セラーリザーブの仕組みを採用する場合には、注意が必要です。
③ 第三者による保険・保証
損害保険会社を利用した保険や第三者による保証であり、社債や借入れの契約上、保有物件に関して損害保険の付保は通常必須のものとなります。
ヴィークルの種類
資産の流動化に使用されるヴィークルを利用方法等によって分類すると、図表のようになります。なお、図表では、ヴィークルおよび組合員等の課税関係の異同により、各ヴィークルを次の(A)、(A’)、(B)、(C)、(C’)に分類します。
(A)ヴィークル自体が原則として法人税課税なし、かつ直ちに組合員課税されるもの(パス・スルー)
(A’)ヴィークル自体が原則として法人税課税なし、かつ直ちに組合員課税されず、分配時に初めて課税されるもの
(B)法定4ヴィークルを中心として90%超配当要件等、条件によっては法人税の課税所得を減らすことができ、結果として法人税課税を減少できるもの(ペイ・スルー)。特定目的会社はこれに該当します。
(C)ヴィークルそのものには法人税が課せられるもの。SPC等として用いる場合には、何らかの工夫が必要です。
(C’)一定の所得について、器そのものには法人税が課せられるもの。なお、人格なき社団等は原則として法人税課税があるが、収益事業より生ずる所得に限られます。外国法人も法人税課税があるが、PEの有無により一部の国内源泉所得に限られます。
【図表】ヴィークルの種類
| ヴィークルの性格 | 通常の会社 Corporation | 資産運用型 Fund | 資産流動化型 Special Purpose Entity |
| 活動の範囲 | 制約なし(買収合併等による大変化も可) | 資産運用に限定(資産追加・入替え可) | 資産保有に限定(資産入替え不可) |
| 発行証券 | 株式や債券等 | 主として持分証券 | ABS(資産担保証券) |
| 信託型 | 一般の事業信託(A) 目的信託(A&C) 特定受益証券発行信託(A’) その他受益証券発行信託(C) | 合同運用信託(A’) 証券投資信託(A’) 国内公募投資信託(A’) 外国投資信託(A’) 特定投資信託(B) | 特定目的信託(B) 受益者等課税信託(A) |
| 法人型 | 事業法人(C) ※合同会社を含む | 投資法人(B) | 特定目的会社(B) 受動的SPC(国内C/外国C’) 人格なき社団等(C’)(収益事業のみ) |
| 組合型 | 任意組合(A)・匿名組合(A)・パートナーシップ(A)・有限責任事業組合(A)・投資事業有限責任組合(A) | ||
お問合せはこちら
公認会計士・税理士 坂口美穂事務所への見積り依頼、業務内容についてのご質問についてのお問い合わせは、メール、もしくはお電話にて対応しております。また、会計・税務・経営・法人設立などに関する相談についても、メールまたは電話等にて無料対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

お気軽にお問合せください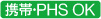
よくあるご質問
- 相談したい時はどうしたらいいんですか?
- 結局費用はいくらかかるの?
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
坂口美穂公認会計士事務所
事務所概要
営業時間
無料相談日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × |
令和8年 2月 9日 ~ 2月15日
営業時間
9:30~18:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
休業日
土曜日・日曜日・祝日
詳しくはお電話ください。
お問合せ・お申込み
お気軽にご連絡ください。
0562-47-6697
お気軽にご相談ください。
詳細はこちら
お問合せはこちら
著書・執筆記事
中部経済新聞
・「住まいづくりのための賢い税金対策」(2012年6月4日)
・「空き家対策と税制」(2017年10月5日)
・「外国人の給与にまつわる税務知識」(2019年3月7日)
・「コロナ禍における税務支援事業」(2021年6月3日)
過去の執筆記事
(近代中小企業)
- 「近代中小企業」2009年5月号(【特集企画】銀行に頼らない経営)
- 「近代中小企業」2011年10月号(【特集企画】中小企業のためのガバナンス!)
- 「近代中小企業」2013年1月号(【特集企画】消費税10%突入に備える、転換期の経営防衛術)
- 「近代中小企業」2014年2月号(【特集企画】社長の終活)
- 「近代中小企業」2015年12月号(【特集企画】直前緊急対策!マイナンバー制度)
バックナンバーのある号がございます。ご興味のある方はお問合せください。
詳細はこちら