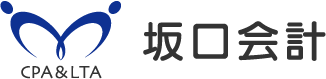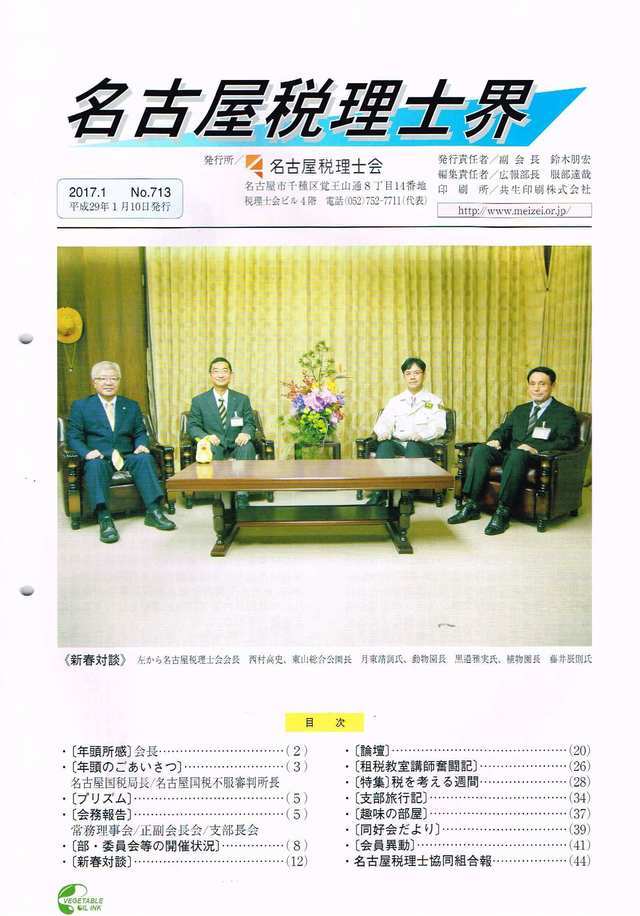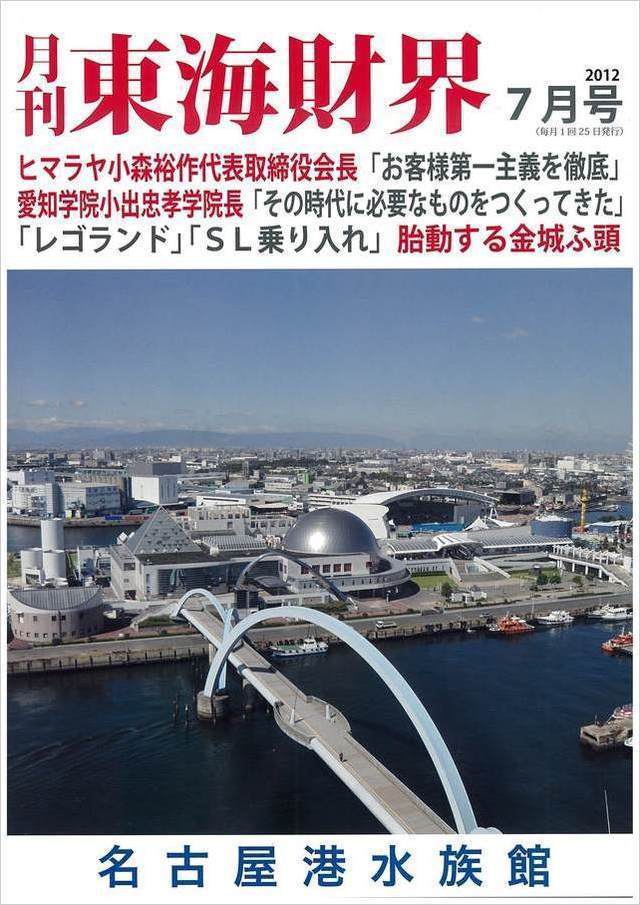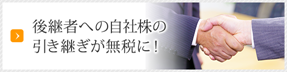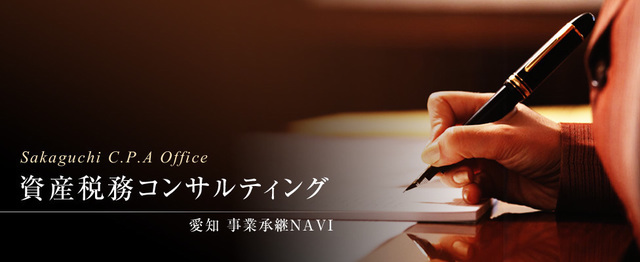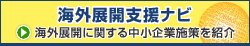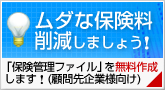愛知県大府市の公認会計士・税理士 坂口美穂事務所。皆さまの最適なファイナンス構築と企業価値向上を支援する会計事務所です。
外国人に対する税務 -確定申告を中心に-
義務者の区分と課税所得の範囲の違い
所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人の四つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。
居住者の課税所得の範囲
居住者とは、日本国内に住所があるか又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人です。
なお、居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。
(1) 非永住者以外の居住者
非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その全ての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。
(2) 非永住者
居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。
非永住者は、国内において生じた所得(国内源泉所得)と、これ以外の所得(国外源泉所得(例えば、国外の預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など))で日本国内において支払われたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。
非居住者の課税所得の範囲
あ居住者以外の個人を非居住者といいます。
非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。
※ 具体的に、居住形態別の課税所得の範囲は次のようになります。
所得区分
居住形態 | 国内源泉所得 | 国外源泉所得 | ||||
国内払 |
国外払 |
国内払 | 国外払 | |||
| 国内に送金された部分 | 国内に送金されない部分 | |||||
居住者 | 永住者 | 課 税 | ||||
| 非永住者 | 課 税 | |||||
| 非居住者 | 原則として課税 | 課税関係は生じない | ||||
居住者と非居住者の国内源泉所得の課税方法の違い
居住者と非居住者の国内源泉所得の課税方法、及び非居住者でもPEを有する場合とPEを有しない場合の課税関係の概要は、以下の資料でご確認ください。
(参考)PEを有しない非居住者の株式等譲渡の課税対象
恒久的施設(PE)を有しない非居住者が株式等を譲渡した場合、次の①~⑥のいずれかに該当する所得が国内源泉所得として課税対象になります。このうち、①~⑤に該当するものについては15%の税率により申告分離課税となり、⑥に該当するものについては総合課税の対象となります。
① 内国法人の株券等の買集めをし、これをその内国法人等に対し譲渡することによる所得
② 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行う、その内国法人の株式等の譲渡による所得
③ 税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡による所得
④ 特定の不動産関連法人の株式の譲渡による所得
⑤ 日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得
⑥ 日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得
したがって、PEを有しない居住者は、上場株式等譲渡所得に係る損失の繰越並びに上場株式配当及び他の口座で行った株式等譲渡等との通算について、上記①~⑥に該当しない限り、確定申告をすることはできません。
なお、PEを有しない居住者は、そもそも特定口座を保有することができません。
おって、これらに該当する場合であっても、租税条約により日本で課税されないことがあります。
居住者と非居住者の所得控除及び税額控除
居住形態により所得控除・税額控除の適用に違いがあるので注意してください。
| 控除の種類 | 居住者 | 非居住者 | 年の中途で変更がある場合 | |
所得控除 | 雑損控除 | ○ | ● | ● |
| 医療費控除 | ○ | × | △ | |
| 社会保険料控除 | ○ | × | △ | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | ○ | × | △ | |
| 生命(地震)保険料控除 | ○ | × | △ | |
| 寄付金控除 | ○ | ○ | ○ | |
| 障害者控除 | ○ | × | ▲ | |
| 寡婦(寡夫)控除 | ○ | × | ▲ | |
| 勤労学生控除 | ○ | × | ▲ | |
| 配偶者(特別)控除 | ○ | × | ▲ | |
| 扶養控除 | ○ | × | ▲ | |
| 基礎控除 | ○ | ○ | ○ | |
税額控除 | 配当控除 | ○ | ○ | ○ |
| 住宅借入金等特別控除 | ○ | × | ■ | |
| 政党等寄付金特別控除 | ○ | ○ | ○ | |
| 外国税額控除 | ○ | ×(注) | □ |
○・・・適用あり
●・・・非居住者である期間については、日本国内に有する資産についてのみ適用あり
△・・・居住者であった期間の支払分についてのみ適用あり
▲・・・次の時期の現況で扶養親族等と判定される場合は適用あり
| 非居住者→居住者 | ― | その年の12月31日の現況 |
居住者→非居住者 | 納税管理人を定めている場合 | その年の12月31日の現況 |
| 納税管理人を定めていない場合 | 出国時の現況 ※ |
※出国後に子どもが生まれた場合、扶養親族になりません。
□・・・非居住者であった期間に生じた所得はないものとみなす
■・・・非居住者となった時点でその年分以降について適用なし
×・・・適用なし
(注)PEを有する非居住者は、PE帰属所得に係る外国税に限り外国税額控除が認められる(平成29年分より)

外国人の方の確定申告の添付書類
外国人の方が確定申告をする際の、添付書類は下記の通りです。
- 源泉徴収票
- 在留カードの写し
- 居住形態等に関する確認書
- 預金通帳等の写し(注)
(注)外国人の方の場合、還付金の受取口座の名義がカタカナ氏名で、確定申告書に記載された氏名と相異していることが多いため、還付金の振込ができなくなるのを防ぐために、任意で口座名義人の分かる箇所をコピーします。
【国外に扶養親族がいる場合】
- 親族関係書類(出生証明書・婚姻証明書等)
- 送金関係書類(送金依頼書・金融機関等の取引明細書)
 注意!
注意!
中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については、一定の期間「在留カード」とみなされます。
中長期在留者は、地方入国管理官署における新たな在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に、在留カードに切り替えることになるため、在留カードが交付されるまでは、引き続き「外国人登録証明書」を所持することになります。
非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合
平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出し、又は提示する必要があります。
詳しくは、下記をクリックしてご確認ください。
非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
確定申告義務者が出国する場合の手続き
納税者が国内に住所を有しなくなる場合に、確定申告書の提出や納税等の必要がるときは、国内に住所等を有する納税管理人を定めなければならないとされています。
| 納税管理人を選任する場合 | 納税管理人を選任しない場合 | |
| 出国時の手続 | 「納税管理人の届出書」を提出 (注1、2) | 準確定申告書(出国時までの所得)を出国時までに提出 |
| 確定申告時の手続 | 確定申告書(居住者期間のすべての所得と非居住者期間の国内源泉所得)を翌年3月15日までに提出 (注2) | 【出国後に国内源泉所得がある場合】 同左 ただし、①所得控除の判定は出国時の現況で判定します。②出国時の納付した予納税額を控除します。(注2) |
(注1)出国時に納税管理人の届出書が提出されてても、出国後に提出された準確定申告書は期限後申告となります。
(注2)届出書や申告書の提出先は納税者の所轄税務署となります。(納税管理人の所轄税務署ではありません。)
非居住者の特殊な申告
非居住者については、次の2つの特殊な申告があります。
退職所得の選択課税の申告
非居住者の退職所得については、国内勤務にかかる収入金額の20.42%の源泉分離課税で、課税関係が終了します。(所法169、170、212①)
しかし、これでは、たまたま海外勤務になった後、そのまま退職した者とずっと国内で勤務していた者とでは、次のような不均衡が生じてしまいます。

退職金の支払額 1,500万円
① 23年間国内勤務し最後の2年間は海外勤務した後、退職したした者の場合
1,500万円×23年/25年=1,380万円
1,380万円×20.42%≒281.79万円
② 25年間ずっと国内勤務で退職した者の場合
(1,500万円ー1,150万円)×1/2=175万円
175万円×5%=87,500円(源泉徴収)
87,500円+87,500円×2.1%≒89,300円
 両者の課税を比べると、2,728,600円の差!
両者の課税を比べると、2,728,600円の差!

この不均衡を是正するため、非居住者は申告することにより、居住者並みの課税とすることができます。(所法171)
計算方法は次の通り居住者と同様ですが、この制度は源泉分離課税の特例のため、居住者の退職所得と違い、所得控除はできません。
(収入金額ー退職所得控除額)×1/2×税率(累進課税)
※ 当該選択課税の申告書は、一般の確定申告書とは独立した申告書であるため、既に総合課税で確定申告書を提出している場合であっても、提出することができます(5年間還付申告が可能)。
所得税法第172条第1項に規定する申告
非居住者が国内勤務に対する給与や報酬の支払いを受ける場合には、支払者が支払額の20.42%を源泉徴収し国に納めますが、支払者が海外にいる場合にはその支払者に源泉徴収義務が無い場合があります。
この場合には、本人が支払額の20.42%を、所得税法第172条第1項、復興特措法17条5項に規定する申告書(以下「172条等申告書」といいます。)を税務署に提出する必要があります。
具体的な申告手続きについては、上記「確定申告義務者が出国する場合の手続き」と同様です。
※ 172条等申告書は、一般の確定申告書とは独立した申告書であるため、不動産所得等がある非居住者については、172条等申告書とは別に、一般の確定申告書も提出する必要があります。
お問合せはこちら
公認会計士・税理士 坂口美穂事務所への見積り依頼、業務内容についてのご質問についてのお問い合わせは、メール、もしくはお電話にて対応しております。また、会計・税務・経営・法人設立などに関する相談についても、メールまたは電話等にて無料対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

お気軽にお問合せください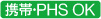
よくあるご質問
- 相談したい時はどうしたらいいんですか?
- 結局費用はいくらかかるの?
- サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。
坂口美穂公認会計士事務所
事務所概要
営業時間
無料相談日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | × | × | × | × | × | × | × |
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × |
令和8年 3月 2日 ~ 3月 8日
営業時間
9:30~18:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
休業日
土曜日・日曜日・祝日
詳しくはお電話ください。
お問合せ・お申込み
お気軽にご連絡ください。
0562-47-6697
お気軽にご相談ください。
詳細はこちら
お問合せはこちら
著書・執筆記事
中部経済新聞
・「住まいづくりのための賢い税金対策」(2012年6月4日)
・「空き家対策と税制」(2017年10月5日)
・「外国人の給与にまつわる税務知識」(2019年3月7日)
・「コロナ禍における税務支援事業」(2021年6月3日)
過去の執筆記事
(近代中小企業)
- 「近代中小企業」2009年5月号(【特集企画】銀行に頼らない経営)
- 「近代中小企業」2011年10月号(【特集企画】中小企業のためのガバナンス!)
- 「近代中小企業」2013年1月号(【特集企画】消費税10%突入に備える、転換期の経営防衛術)
- 「近代中小企業」2014年2月号(【特集企画】社長の終活)
- 「近代中小企業」2015年12月号(【特集企画】直前緊急対策!マイナンバー制度)
バックナンバーのある号がございます。ご興味のある方はお問合せください。
詳細はこちら